石井眞治
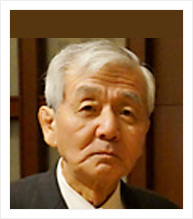
石井 眞治
AISES最高顧問
比治山大学学長を経て、現職。
主な専門分野は教育心理学、生活指導・
生徒指導、教師教育。元広島大学教育開発国際協力研究センター長、
広島大学副学長、ケニアの教育開発担当者(JICA:国際協力機構)、
広島市教育委員長(8年)、広島大学大学院教授なども歴任しており、実に多様な経験をもつ。
その幅広い視野と国際性から日本の生徒指導や教育行政の在り方について
提言を行っている。
主な著書に『児童・生徒のための学校環境適応ガイドブック-学校適応の
理論と実践-』(協同出版)など多数。
主な論文に「教員採用試験の合否に影響を及ぼす諸要因に関する研究-
比治山大学教職指導センターのサポート業務と受験生の対人的環境についてー」
(比治山大学現代文化学部紀要)等がある。
エリクソン ユキコ
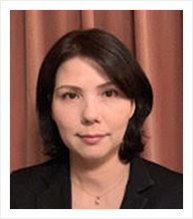
エリクソン ユキコ
学校教育開発研究所 理事・カウンセラー、広島大学大学院人間社会科学研究科附属教育実践総合センター客員准教授。
臨床心理士として医療・療育・教育・産業など様々な分野で臨床活動を行う。
また、カウンセリング技術や心理教育的アセスメントなど学校臨床心理学関連領域で講義を行うだけでなく、産業や労働の現場で使えるカウンセリング技術などの講演も行う。
また、学校心理教育支援室で相談活動を行っている。
主な論文に「カウンセリング技法を活用した共同学習の効果検討―導入期における成果と課題―」(学校教育実践学研究)、「学校臨床相談支援員のケースに対する意識変容:学校心理教育支援室「にこにこルーム」の事例から」(学校教育実践学研究)がある。
沖林洋平

沖林 洋平
山口大学教育学部准教授。
広島大学大学院教育学研究科博士後期課程修了、広島大学大学院学習開発学講座助教を経て、現職。
主な専門分野は、教授・学習心理学。
特に批判的思考が主な研究テーマ。
教育心理学と教育工学を専門に、協同学習や批判的思考力の育成をテーマに研究を展開。
教員研修の効果測定を通じ、質の高い60時間以上の研修の重要性を提唱し、反転授業やICT活用を通じて教育の質向上を目指している。
主な著書に『マルチレベルアプローチ だれもが行きたくなる学校づくり 日本版包括的生徒指導の理論と実践』(ほんの森出版)がある。
主な論文に「知的好奇心と授業に対する興味と学習内容の定着の関係」(日本教育工学会論文誌)、「ガイダンスとグループデイスカッションが学術論文の批判的な読みに及ぼす影響」(教育心理学研究)等がある。
川俣智路

川俣 智路
北海道教育大学教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)准教授
北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程修了後、北海道大学大学院教育学研究科附属子ども発達臨床研究センター、大正大学心理社会学部を経て、現職。
公認心理師、北海道スクールカウンセラー。
アメリカのCASTが提唱している「学びのユニバーサルデザイン(UDL)」枠組みによる学習環境デザインを通じて、主体的な学習者の育成に取り組んでいる。
近年の業績として「革命のヴィゴツキー もうひとつの「発達の最近接領域」理論」(共訳 新曜社 2020)、「Educating Adolescents Around the Globe: Becoming Who You Are in a World Full of Expectations (Cultural Psychology of Education (11)) 」(共著、Springer、2020年)「ユニバーサルデザインを援用した修学・就労支援─不登校生との事例から─」(思春期青年期精神医学 第30巻1号 2020)、「学校における支援の視点」(そだちの科学 第34巻 日本評論社 2020 )、「学習支援から学習者の発達支援へ─UDLを支える足場的支援(Scaffolding)」(指導と評価 第66巻2月号 2020)、「キーワードで読み解く 特別支援教育・障害児保育&教育相談・生徒指導・キャリア教育」(共著 福村書店 2020)などがある。
神山貴弥

神山 貴弥
同志社大学心理学部教授。
広島大学大学院教育学研究科准教授を経て、現職。
教育心理学と社会心理学を専門に、学校適応や生徒指導の発展に尽力。
学級内の仲間関係や異年齢交流をテーマに研究を進め、包括的生徒指導「マルチレベルアプローチ」の普及に取り組む。
研修活動や、学校教育活動への助言・提言を通じ、学術的知見を社会に還元している。
主な著書に『心理学概論[第2版]』(編著・ナカニシヤ出版)、『児童・生徒のための学校適応ガイドブック―学校適応の理論と実践―』(編著・協同出版)など多数。主な論文に、「学校学習環境が生徒の主体性およびスクール・モラールに及ぼす影響」(同志社大学教職課程年報)等がある。
小玉有子

小玉 有子
弘前医療福祉大学保健学部看護学科教授。
公立学校養護教諭、弘前大学教育学部非常勤講師、小中高等学校のスクールカウンセラーを経て、現職。
主な専門分野は臨床心理学、発達心理学、カウンセリング論、発達障害、健康相談など多数。
養護教諭・教育相談主任・特別支援コーディネーターの経験と臨床心理学を踏まえながら、実際の学校でスクールカウンセラーとして、また高等学校や教育委員会等のスーパーバイザーとしても活動している。
現在は、学校不適応(非社会・反社会)への心理臨床的アプローチ、発達障害あるいはグレーゾーンと言われている児童生徒の学校適応や就労支援に取り組んでいる。
主な著書に『学校教育相談ハンドブック』(日本学校教育相談学会)など多数。
主な論文に「包括的アプローチの枠組みから見たフィンランドの教育~生徒指導先進地域の実践比較研究~」(弘前医療福祉大学紀要)、「イギリスにおける愛着に課題を持つ子どもたちへの対応と日本の教育への示唆」(弘前医療福祉大学紀要)等がある。
鈴木建生

鈴木 建生
ユマニテク短期大学幼児保育学科学長。
三重県立高校、定時制高校など35年間の高校教諭を経て、産業能率大学経営学部教授。
2017年ユマニテク短期大学副学長、2019年から現職。
キャリア教育にコーチングと協同学習を活用し、多くの困難を抱える若者のキャリア教育の実践研究を行う。
キャリア教育を担う教師自身のキャリア教育の必要性を提唱する。
授業改善を中心にスーパーバイザーとして全国の高校教育改革の活動をしている。
主な著書に、『インターンシップの手引き』(三重県教育委員会)、『この一冊で分かるアクティブラーニング入門』(PHP出版)、『「総合的な探究」実践ワークブック 社会で生き抜く力をつけるために』(学事出版)等がある。
髙橋あつ子

髙橋 あつ子
早稲田大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)教授。
公立小学校教諭、公立総合教育センター指導主事、公立小学校教頭を経て、2008年より早稲田大学教職大学院准教授を経て、2015年から現職。
臨床心理士、公認心理師、学校心理士スーパーバイザー、特別支援教育士スーパーバイザー。
インクルーシブ教育や多文化共生を推進。
「学びのユニバーサルデザイン(UDL)」実践を牽引。日本学校教育相談学会で長らく研修委員を歴任し、巡回相談や校内研修、私学の特別支援教育に貢献。
著書や論文で教育現場の課題解決を支援している。
学校教員経験、教育委員会指導主事経験をもつ。
主な著書に『一から始める特別支援教育『校内研修』ハンドブック』(明治図書)、共著『発達に偏りのある子のトラブルを減らす自己理解イラスト教材』(ほんの森出版)、編著「私学流 特別支援教育」(学事出版)など多数。主な論文に「特別支援教育と支援の方法(特集対人援助職の必須知識スクールカウンセリングを知る-個別の具体的展開の方法)」(臨床心理学)、「危機状況から脱した教職員の変容プロセス」(学校教育相談研究)等がある。
中井悠加

中井 悠加
島根県立大学人間文化学部保育教育学科講師。
広島大学大学院教育学研究科・特任助教、同・助教、島根県立大学短期大学部・講師を経て、現職。検定教科書『みんなと学ぶ小学校国語』(学校図書)編集委員。
教科教育学および初等中等教育学を専門とし、詩創作指導や創造性育成に注力。
国語教育の中で「詩創作デジタルスペース」を活用した新たな学びの形を提案し、言葉のティンカリングを通じた創造的な学習環境の構築を目指している。
「持続可能な学び合い」や「批判的読解力」の育成をテーマに研究を進め、自己決定理論に基づくワークショップ形式の授業開発に尽力。
特別支援教育にも関与し、包括的学習支援アプローチの開発を推進している。
国語科教育の枠を超えた実践と研究で国内外から注目を集めている。
主な著書に『中学校・高等学校 文学創作の学習指導』(共著・渓水社)、『学びを創る教育評価』(共著・あいり出版)等がある。
主な論文に「S.Dymokeの詩創作指導の理論と方法 : 下書きと評価を中心に」(『国語科教育』)、「ワークショップ型詩創作指導による学びの形成:Arvon Foundationの取り組みの検討から」(『学校教育実践学研究』)等がある。
中林浩子
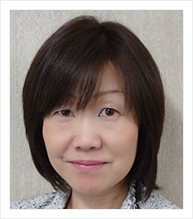
中林 浩子
下関市立大学 特別支援教育特別専攻科 教養教職機構 教授
公立中学校教諭、生徒指導長期派遣研修員、教育相談センター(教育センター兼務)指導主事、公立中学校教頭、公立小学校校長を経て、現職。
日本学校教育相談学会事務局次長。
中学校・小学校・指導主事・管理職の経験を活かし、学校現場における包括的生徒指導・教育相談の実装支援、教育委員会や学校と共同した研修プログラムの提供および教師の力量形成に取り組んでいる。
主な著書に「マルチレベルアプローチ だれもが行きたくなる学校づくり日本版包括的生徒指導の理論と実践」(分担執筆 ほんの森出版)等がある。
中村孝

中村 孝
比治山大学准教授
日本ピアサポート学会,、研究紀要委員会理事
教育心理学と生徒指導を専門に、通信制高校校長を歴任し、不登校やいじめ問題と直接関わってきた経歴を持つ。
代表理事(栗原)とは共同でB-SAFEプログラムを開発。
国内外での講演活動を通じ教育現場に貢献している。
主な論文に「入試形態による入学後の学業成果の差と入学前の伸長意向別にみた4×3の比治山力の伸長具合の差の検証」(比治山大学紀要)、「国際的なイベントボランティアに参加する学生の特徴と参加後の学びや成長を表す特徴語」(比治山大学短期大学部紀要)などがある。
山崎茜

山崎 茜
広島大学大学院教育学研究科教職開発講座(教職大学院)講師。
広島大学大学院教育学研究科博士後期課程修了後、広島大学大学院教育学研究科附属教育実践総合センター客員准教授を経て、現職。
学校心理士、広島市・総社市スクールカウンセラー。
教育心理学を専門に、友人関係や愛着の発達をテーマに研究を展開。
東広島市や企業などと共同し,不登校や子育て支援の社会実装を目指した取り組みにも参画している。
全国で教員研修や講演活動を行い、包括的生徒指導や教育相談の普及に尽力している。
主な著書に『愛着関係の発達の理論と支援』(共著・金子書房)、『はじめて学ぶ生徒指導・進路指導』(共著・ミネルヴァ書房)がある。
主な論文に「愛着に課題のある子どもを育て直す「チーム学校」の可能性−子どもの愛着に関する研究の動向と課題から−」(学習開発学研究)等がある。
山田洋平

山田 洋平
福岡教育大学 大学院教育学研究科 教職実践研究ユニット 准教授
福岡教育大学研究補佐員、梅光学院大学子ども学部子ども未来学科講師、島根県立大学人間文化学部保育教育学科准教授を経て、現職。
主な専門分野は学校心理学、教育相談。
SELを基盤にした心理教育プログラムを普及。
感情理解やコミュニケーション能力育成をテーマに研究を進め、日本教育心理学会優秀論文賞を受賞。
全国で講演活動を行い、教育現場に貢献している。
主な著書に『社会性と情動の学習(SEL‐8S)の進め方――小学校編 (子どもの人間関係能力を育てるSEL‐8S)』『同――中学校編』など。
主な論文に「小中学生用規範行動自己評定尺度の開発と規範行動の発達的変化」(教育心理学研究)等がある。
米沢崇

米沢 崇
広島大学大学院教育学研究科准教授。
広島大学大学院教育学研究科博士後期課程修了、奈良教育大学教育学部准教授を経て、現職。主な専門分野は教師教育学。
どうしたら実際の学校がよくなるのか、教師の力量が向上するのかを教師教育と学校経営学の観点から研究している。
また野外活動、地域の子供達を集めた活動、総合的な学習についても、実際に活動に参加して指導をしており、こうした領域についても幅広い知見を持つ。
主な著書に『児童・生徒のための学校環境適応ガイドブック』(協同出版)がある。
主な論文に「『初任者の授業力向上のための実践ハンドブック』の開発」(広島大学大学院教育学研究科)等がある。
金山健一

金山 健一
神戸親和女子大学大学院文学研究科教授。
公立中教諭,県立広島大学総合教育センター准教授を経て、現職。学校心理士・臨床心理士。主な専門分野は学校心理学・臨床心理学。
博士(心理学)、臨床心理士としていじめ、不登校への予防的生徒指導を提唱。
文部科学省技術審査委員会専門員ネット問題担当、こども家庭庁企画分析会議委員や、総務省インターネット・リテラシー 検討委員として政策立案に関与。
「「非行」や「ネット問題」の解決に向けた実践的な教師のワザを広め、その活動は国内外で評価される。
神戸市いじめ問題審議会委員長。
主な著者に『気になる子と関わるカウンセリング(チャートでわかるカウンセリング・テクニックで高める「教師力」)』(ぎょうせい)、ブリーフセラピーの技法を越えて-情動と治療関係を活用する解決志向アプローチ-イブ・リプチック著(金剛出版)など多数。


栗原 慎二
広島大学名誉教授・学校教育開発研究所代表理事。
博士(学校教育学)を持ち、生徒指導提要の改訂や包括的生徒指導アプローチ「MLA」を提唱。
不登校支援やピアサポートを中心に国内外で高く評価される実践を展開。
教育相談コーディネーターとして、解決思考ブリーフセラピーや交流分析を背景にアセスメント手法を活用し、高校教員から大学教員まで幅広いキャリアを積む。
日本学校教育相談学会 元会長。
日本スクールカウンセリング推進協議会 顧問。アセス・B-SAFE開発者。
主な著書に『いじめ防止6時間プログラムいじめ加害者を出さない指導』『アセスの使い方・活かし方』(ほんの森出版)など多数。
主な論文に「マルチレベルアプローチ日本版包括的生徒指導の理論と実践」(月刊学校教育相談)等がある。







 LINEに追加する
LINEに追加する