
このような悩みがクローズアップされています。(一例)
-
公立小学校校長

悩み
近年、学校のいじめや不登校の問題が増加し、文科省や保護者からのプレッシャーが大きくなっている。学校全体の教育の質を向上させたいが、教師の負担を増やさずに実施できる効果的な方法が見つからない。
願望
いじめや不登校を減らし、学校の風評を良くすることで、地域の信頼を得たい。
-
中学校学年主任

悩み
学校外でのSNSトラブル等が引き金になり、日中のクラスの雰囲気がギスギスしている。いじめの兆候を見逃したくないが、生徒全員の心理状態を把握するのは極めて困難。教師の目だけでは限界を感じる。
願望
生徒たちの本音を知り、安心して学べる環境を作りたい。特に問題のあるクラスの雰囲気を改善し、学年全体の雰囲気を良くしたい。
-
PTA会長

悩み
保護者間で「いじめ問題が深刻化している」「学校が対応してくれない」といった不満が噴出。PTAとしても何かできることはないかと模索しているが、具体的な手立てがない。
願望
自分の子どもだけでなく、学校全体の教育環境を改善し、安心して通える学校を作りたい。
-
教育委員会の指導主事

悩み
地域の小中学校でいじめや不登校が問題になっており、なんとか現場の先生方の力になりたい。その一方で、学校現場の様子や通っている子どもの気持ちまで把握できないため、具体的な対策が打てていない。
願望
データを活用して学校ごとの課題を分析し、自治体全体の教育環境を改善したい。学校への指導やサポートを的確に行いたい。
-
スクールカウンセラー

悩み
生徒一人ひとりにじっくり寄り添いたいが、先生方との情報共有の時間が足りない。教師からの相談も多く、限られた情報の中で的確な支援をするのが難しい。
願望
事前に生徒の心理状態や様子を把握し、面談の優先順位をつけられるようになりたい。また、SOSを早期に発見し、問題が深刻化する前に対応したい。
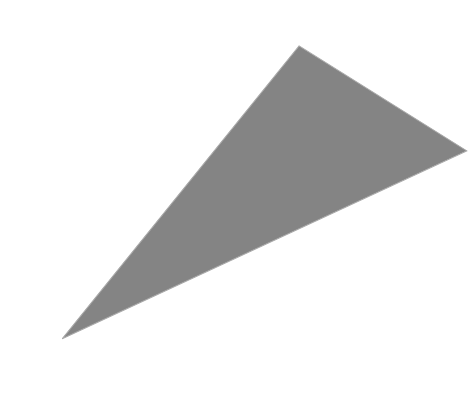
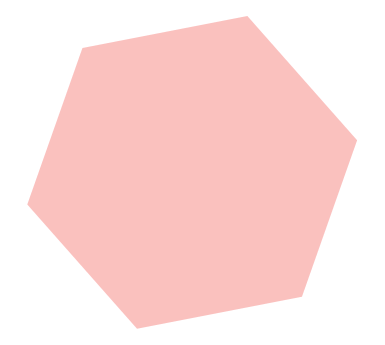
-
いじめや不登校が増えているのに、事前に兆候をつかめず、
対応が後手になってしまう…いじめや不登校が表面化してからでは遅い。水面下に潜むSOSをつかむ方法がなく、日々不安を感じていませんか?
-
保護者から『学校は何もしてくれない』とクレームが来るが、具体的な対策を示せない…
いじめや学級の雰囲気をどう改善しているかを、保護者に説明できず困っていませんか?
-
生徒一人ひとりの本音が見えず、
教師の勘や経験に頼るしかない…子どもたちの悩みやストレスを「教師の目」と「客観的なデータ」の両面から的確に把握できたらと思いませんか?
-
学級の雰囲気がギスギスしているのに、
どこから手をつければいいのかわからない…なんとなく空気が悪いと感じても、具体的な改善策を打ち出せずにいませんか?
-
『いじめ・不登校対策の強化』『プロアクティブな生徒指導』と言われ手は打っているが、効果が見えにくい
形だけのアンケートではなく、本当に効果が出る対策、「成果の見える化」を探していませんか?
-
スクールカウンセラーの時間が限られていて、
支援が本当に必要な子を見極められない…すべての生徒と話すのは不可能。でも、誰を優先すべきか判断する方法がないと感じていませんか?
-
教師ごとに生徒へのアプローチがバラバラで、学校全体で一貫した対応ができない…
各教師の経験や価値観に頼るのではなく、データをもとに一貫した指導をしたいと思いませんか?
-
学校全体の課題を把握したいが、客観的なデータがなく、具体的な方針を決められない…
感覚ではなく、数字で課題を可視化できたらと思いませんか?
-
毎年の学級経営が手探り状態で、特に新学期はどうすればいいのか分からない…
学級の問題点をすぐに把握し、スムーズに学級経営をしたいと思いませんか?
-
生徒の学校適応感や人間関係がうまくいっているか分からず、不安を感じる…
本当に子どもたちは安心して過ごせているのか、データで把握できたらと思いませんか?
これらの悩みは、学校現場で教育に関わる人々が日々感じているリアルなものです。
悩みが解決できない理由

- 「教師の経験や勘に頼るしかない環境」
- → 客観的なデータがない
- 「問題の兆候を見抜く仕組みがない」
- → いじめや適応感の低下が表面化しないと気づけない
- 「統一されたアプローチがなく、対応がバラバラ」
- → 学校全体での共通認識がない
- 「従来のアンケートや面談では本質が見えない」
- → 生徒が本音を言えない仕組み
「子どもたちの本当の声が聞こえていますか?」
いじめや不登校が増える中、教師や教育関係者の皆さんは、「もっと早く兆候に気づけていたら…」と後悔したことはありませんか?
しかし、生徒の本音は簡単には見えません。従来のアンケートでは核心に触れられず、教師の観察だけでは限界があります。
その結果、問題が表面化したときにはすでに手遅れになっているのです。
「アセス・B-SAFE」は、そんな教育現場の課題を解決するために生まれました。
アセス・B-SAFE –
いじめ予防と学級改善のためのツール
子どもたちの未来のために:アセスとB-SAFEに込められた願い
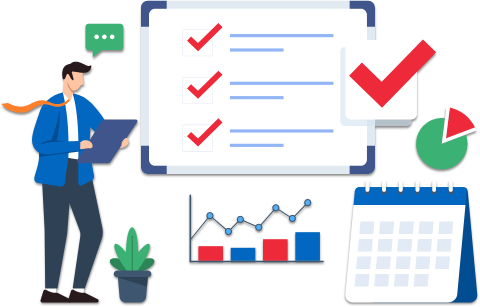
学校の課題に真正面から向き合う新しいツール
学校は、子どもたちが安心して学び、成長する場であるべきです。しかし、現代の教育現場では、不登校やいじめ、学級内の人間関係の悪化など、さまざまな課題が顕在化しています。こうした課題に気づくのが遅れれば、子どもたちの心の傷が深まるだけでなく、教育現場全体の環境も悪化してしまいます。
**「アセス」と「B-SAFE」**は、こうした問題に真正面から向き合うために開発されたツールです。アセスは、子どもたちの学校適応感を数値化し、個々の状況を詳細に把握するためのアセスメントツールです。一方、B-SAFEは、いじめの実態把握と予防に特化し、学級の環境改善をサポートするツールです。
誰一人取り残さない教育を実現するために、私たちはアセスとB-SAFEを提供します。
アセスとは?
– 子どもの学校適応感を見える化するツール
学校生活で子どもたちがどのように感じ、どれだけ適応しているかを把握する――アセス(ASSESS)は、この「見えにくい部分」を明らかにするために開発されたツールです。
アセス(Adaptation Scale for School Environments on Six Spheres)は、子どもたちの学校適応感を測定するために開発されたアセスメントツールです。学校生活において子どもたちがどのように感じ、どの程度「自分は適応できている」と感じているか、子どもの目線に立って以下の6つの側面から多面的に理解することができます。
-
生活満足感
学校生活全体への
満足度 -
教師サポート
教師からの支援を
どの程度感じているか -
友人サポート
友人関係の充実度
-
非侵害的関係
いじめや
被害感がないか -
向社会的スキル
思いやりや
協力行動の能力 -
学習的適応
学習に対する
取り組みや成果
アセスの最大の特長は、子どもたち自身の主観的な感覚を重視している点です。教師の観察だけでは見えない部分を補完し、子どもたちの本当の声をデータとして可視化します。これにより、学級経営や個別支援の質を向上させることができます。

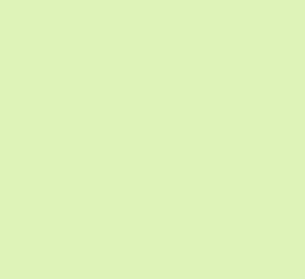
アセスの特徴:
子ども理解を深めるためのツール
アセスは、子どもたちの学校適応感を多面的に測定するツールです。現在は、ダウンロード版とWEB版がありますが、特にWEB版になるとHR等で実施したら、職員室に戻ってすぐに結果を確認し、その日中にSOSに対して介入することが可能です。教員の負担を軽減しながら、見えにくい課題を浮き彫りにし、支援の優先順位を明確にします。アセスの最大の特徴は、子どもたちの学校適応感を多面的に評価できる点です。これにより、個別支援だけでなく、学級全体の改善や早期の問題解決にもつながります。以下の3つがアセスの主な特徴です。
特徴
-

多面的な評価
アセスでは、子どもたちの学校適応感を6つの視点(生活満足感、教師サポート、友人サポートなど)から評価します。この多面的なデータにより、子ども一人ひとりの状態や学級全体の傾向を把握することが可能です。
-

短時間でのデータ取得
アセスは、約5~10分でデータを取得できるため、教員や子どもたちへの負担を最小限に抑えます。効率的にデータを収集し、迅速な対応につなげることができます。
-

結果の見える化と活用
アセスの結果は、個別の子どもだけでなく、学級全体の傾向も見える化されます。これにより、学級経営の改善や支援計画の策定に役立つ具体的な指針を得ることができます。
アセスの活用メリット
- ・子どもの「見えない声」を可視化
- ・学級全体の改善に貢献
- ・具体的な支援の方向性を明確化

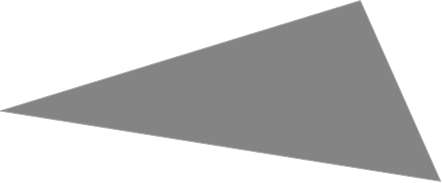
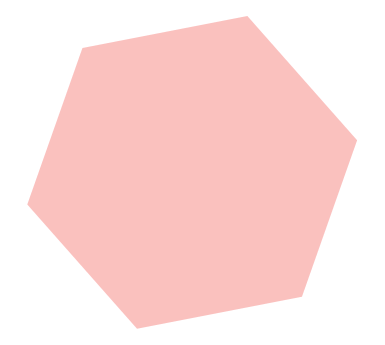
アセスの6尺度:
子どもの学校適応感を深く理解する

生活満足感
子どもたちが学校生活全体に満足しているかを測定します。日常生活全体の幸福感や充実感を把握することで、子どもたちの心の健康状態を確認します。
教師サポート
教師からの支援やサポートを、子どもがどの程度感じているかを測定します。子どもが感じる教師への信頼、“重要な他者”としての認識は、効果的な指導や学級経営の基盤となります。
友人サポート
困った時に「大丈夫?」と気にかけてくれるような友人、友人からのサポート具合をどの程度感じているか測定します。友人とのつながりは、子どもたちの安心感や学校生活の楽しさを支える大きな要素となります。
非侵害的関係
いじめや被害感(言われている気がする、も含む)がないかを確認します。安全で安心できる環境は、子どもたちが学びに集中できる基盤です。
向社会的スキル
思いやりや協力行動に対する自己評価を数値化します。このスキルは、学級や学校全体の風土形成に寄与し、子どもたちの社会性を育むために重要です。
学習的適応
「学習」「学習に向かう姿勢」に対する自分の認識について測定します。「難しい問題でも粘り強く諦めない」気持ちの充実は、将来の学びにも良い影響を与えます。
アセスの6尺度を活用することで、以下のような具体的な支援が可能になります
生活満足感の低い子どもへの支援
学校生活に不満を抱える子どもには、個別面談や活動への参加機会を増やすなどの支援を行います。
非侵害的関係が弱い学級の改善
学級全体でいじめのリスクが高い場合は、協力活動や対話の場を設け、安全な環境づくりを進めます。
アセスの質問例:
「子どもの本音を引き出す34の問い」
アセスの質問は、子どもたちが学校生活で感じていることを引き出し、適応感を測定するために設計されています。短時間で実施可能な34の質問が、支援の第一歩をサポートします。
アセスでは、子どもたちの学校適応感を測定するために、34の質問を用意しています。これらの質問は、子どもたちが普段の学校生活で感じていることを引き出し、6つの尺度に基づいて評価されます。
例えば、以下のような質問があります:
「担任の先生は、私のことをわかってくれている」
「友だちは、嫌なことがあったときに慰めてくれる」
「なんとなく気持ちが落ち着かないことがある」
「勉強のやり方がよくわからない」
「落ち込んでいる友だちがいたら、その人を元気づける自信がある」
これらの質問は、子どもたちにとって答えやすく、短時間で実施可能な構成となっています。また、回答内容は教師の観察だけでは気づけない子どもたちの本音を反映しているため、より深い理解につながります。
アセスの質問を通じて得られるデータは、子どもたち一人ひとりの状態を把握し、適切な支援を行うための貴重な情報源となります。
ライスケールとは?
回答の信頼性を確保する仕組み
アセスでは、子どもたちの回答の信頼性を確保するために「ライスケール」を採用しています。この仕組みにより、より正確な子どもの気持ち理解が可能になります。
ライスケールとは、因子分析によって関連性の高い質問を複数設け、その回答の一貫性を検証する方法です。 例えば、同じ内容を異なる表現で尋ねた場合、矛盾した回答が多い場合には「回答の信頼性が低い」と判断されます。このようなケースでは、以下のような背景が考えられます。
・正直に答えられない心理的な防衛反応や自己開示への不安
・質問内容を理解できていない可能性
アセスにとってライスケールは、信頼性を支える重要な要素であるとともに、回答に矛盾が起きてた子どもも実は支援の対象である、と認識するサインでもあると言えます。
教師が子どもたちの本当の声に耳を傾け、適切な支援を届けるための大切な仕組みといえます。
適応と適応感の違い:
見えないSOSに気づくために

「学校で問題なく過ごしているように見える子どもが、実は心の中でSOSを出していることもある。」適応と適応感の違いを理解することで、見落としがちな課題に気づくことができます。
「適応」と「適応感」は似ているようで異なる概念です。適応とは、外部から見て子どもが学校生活にうまく馴染んでいるかどうかを指します。一方、適応感は、子ども自身が「自分は学校でうまくやれている」と感じているかどうかを示します。
例えば、授業中に静かに座り、特に目立った問題行動を起こさない子どもがいたとします。一見「適応している」と見えるかもしれませんが、その子が「友だちがいない」「先生に理解されていない」と感じている場合、その子の適応感は低い可能性があります。このギャップに気づけないと、問題が顕在化したときには対応が遅れてしまうことがあります。
アセスは、子どもたちの主観的な適応感を測定することで、このギャップを浮き彫りにします。教師の観察だけでは見えない「心の小さなSOS」をキャッチし、早期支援につなげることが可能です。
適応感を重視することは、子どもたちが安心して学校生活を送るための第一歩です。誰一人取り残さない教育を実現するために、適応感という視点を取り入れることが重要です。
COCOLOプランが示すアセスメントの重要性:
チーム学校で子どもを支える
新生徒指導提要やCOCOLOプランでは、チーム学校で子どもを支えるためにアセスメントの重要性が強調されています。アセスは、その実現に向けた強力なツールです。
2022年に改訂された新生徒指導提要や、文部科学省が推進する「COCOLOプラン」では、「子ども理解」の重要性が強調されています。これらの政策は、学校全体がチームとなり、子どもを支える体制を構築することを目指しています。
特にCOCOLOプランでは、不登校やいじめの早期発見と対応が重要視されており、「学校風土の見える化」や「心の小さなSOSを見逃さない仕組みづくり」が求められています。アセスは、こうした目的を達成するための具体的なツールとして注目されています。
アセスは、子どもたちの学校適応感を6つの視点から多面的に測定することで、個々の課題を可視化します。これにより、教師や学校全体が子どもたちの状態を客観的に把握し、適切な支援を講じることが可能になります。また、データに基づく共通認識を持つことで、チーム学校としての一貫した支援体制を構築することができます。
COCOLOプランが掲げる「誰一人取り残さない学び」を実現するために、アセスは欠かせないツールです。教育現場におけるアセスメントの導入は、子どもたちの未来を守るための重要な一歩となります。

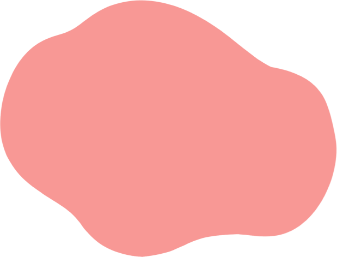

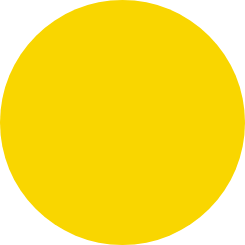
B-SAFEとは?
いじめアンケートを超えた新しいアプローチ

いじめの実態を把握するだけでなく、予防や環境改善までを視野に入れる。それがB-SAFEです。いじめアンケートとの違いを明確にしながら、より効果的な学級づくりを支援します。
B-SAFE(Scale for Better class on Skills, Actions, Friends/teachers and Experiences)は、いじめの予防と対策に特化したアセスメントツールです。従来のいじめアンケートが「いじめの有無」や「加害者・被害者の特定」に焦点を当てていたのに対し、B-SAFEは、いじめの背景や予兆、学級全体の環境改善にまで踏み込んでいます。
B-SAFEが提供する情報は以下の通りです:
子どもたちに必要なスキルの有無(例:自己主張や共感力)
いじめに関する実態(いじめの発生状況やリスク要因)
学級や学校の取り組みの十分性(いじめを未然に防ぐ環境が整っているか)
さらに、B-SAFEは、いじめが「まだ起きていない状態」でもそのリスクを予測し、具体的な予防策を提案する点が特徴です。例えば、「学級内での非侵害的関係が弱い」というデータが示された場合、教師が早期に介入し、学級の人間関係を改善するための指導を行うことができます。
B-SAFEは、単なるいじめアンケートではなく、いじめのない安全な学級を作るための包括的なツールです。教師一人では気づきにくい学級の課題を見える化し、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを支援します。
B-SAFEの特徴:
いじめ予防と学級改善のための新しい視点

B-SAFEは、いじめの予防と学級環境の改善を目的としたツールです。リスクを予測し、具体的な改善策を提案することで、より安全な学級づくりをサポートします。
B-SAFEの最大の特徴は、いじめの予防と学級環境の改善に特化している点です。従来のいじめ対策が「発生後の対応」に重点を置いていたのに対し、B-SAFEは「発生前の予防」に焦点を当てています。
B-SAFEの主な特徴は以下の通りです:
リスク予測
いじめが発生する前に、学級内のリスク要因を特定します。例えば、子どもたちの非侵害的関係や友人サポートの不足がリスクとして示される場合、教師が早期に介入し、環境改善を図ることが可能です。
多面的なデータ分析
いじめの有無だけでなく、学級全体の関係性や子どもたちのスキル(例:共感力、協力行動)を評価します。これにより、学級全体の改善ポイントが明確になります。
具体的な改善指針
B-SAFEの結果は、教師が具体的に何をすべきかを示唆します。例えば、「友人サポートが低い場合は、協力活動を増やす」「非侵害的関係が弱い場合は、対話の機会を増やす」といった具体的な指導案が得られます。
B-SAFEは、いじめのない学級づくりを目指す教師の強力なパートナーです。子どもたちが安心して成長できる環境を作るために、B-SAFEは欠かせないツールとなるでしょう。
B-SAFEの質問例:
いじめ予防と学級改善を支える具体的な問い

B-SAFEでは、子どもたちの学級環境やいじめリスクを把握するために、具体的かつ答えやすい質問を用意しています。これにより、学級全体の課題を浮き彫りにします。
B-SAFEの質問は、いじめの実態やリスクを把握し、学級環境を改善するために設計されています。質問は子どもたちが答えやすい形式で構成され、短時間で実施可能です。
以下は、B-SAFEの質問例です:
「クラスで困っていることがあったとき、助けてくれる友だちがいる」
「みんなの前で意見を言うと、からかわれることがある」
「先生は、クラスのみんなが安心して過ごせるようにしている」
「誰かが困っているとき、どうすればいいかを考えることができる」
「クラスで何か嫌なことがあったとき、それを誰かに相談できる」
これらの質問は、子どもたちの人間関係や学級の雰囲気、教師のサポートの状況を多面的に評価するためのものです。また、いじめが発生している場合だけでなく、発生リスクが高い場合にも、それを予測するデータを提供します。
B-SAFEの質問は、学級の課題を明確にし、教師が具体的な改善策を講じるための第一歩となります。子どもたちの安全と安心を守るために、B-SAFEは重要な役割を果たします。
アセス・B-SAFEの費用:
効果的な支援を手頃な価格で
アセスとB-SAFEは、教育現場での課題解決をサポートするために、リーズナブルな価格設定を実現しました。これにより、全国の学校や自治体が導入しやすくなっています。
| プラン (児童生徒一人当たり) |
学校価格 (税込) |
自治体一括購入価格 (税込) |
|---|---|---|
| アセスWEB版(1回) | 275円 | 138円 |
| アセスWEB版(年3回) | 660円 | 330円 |
| B-SAFE(1回) | 275円 | 138円 |
| B-SAFE(年3回) | 660円 | 330円 |
| アセスWEB版・B-SAFE セット(年3回) |
1,100円 | 550円 |
※自治体一括で導入すると、半額になります。
※アセスWEB版の導入・運用に関して最低限の安全弁として、導入時に各学年1冊「アセスの使い方・活かし方」(ほんの森出版/2,750円)を購入いただきます。
導入プラン
学校単位での導入だけでなく、自治体単位での一括導入も可能です。また、オンライン説明会に参加すると、体験デモ版を2週間無料で利用できる特典もあります。
費用対効果
アセスとB-SAFEは、リーズナブルな価格ながら、子どもたちの適応感やいじめリスクを可視化し、早期支援につなげることができます。これにより、不登校やいじめの予防、学級経営の改善など、教育現場全体の質を向上させることが可能です。
アセスとB-SAFEは、費用対効果の高いツールとして、多くの学校や自治体から支持されています。子どもたちの未来を守るために、ぜひ導入をご検討ください。
体験デモ版(無料)申し込む
導入自治体の声:
アセスとB-SAFEがもたらした変化
-

中学校での活用事例
「アセスを導入することで、不登校傾向の生徒の状態を早期に把握し、家庭との連携を強化することができました。教員間で課題を共有し、個別支援計画の質が向上しました。」(中学校教員)
-

小学校での活用事例
「B-SAFEを活用することで、学級内の人間関係の問題を早期に発見し、いじめの予防につながりました。学級経営に対する意識が向上し、教師同士の連携も強化されました。」(小学校教員)
-

自治体全体での取り組み
「自治体単位でアセスとB-SAFEを導入したことで、地域全体の教育課題をデータに基づいて分析できるようになりました。これにより、学校ごとの支援計画がより具体的で効果的になりました。」(教育委員会担当者)
これらの声は、アセスとB-SAFEが教育現場での課題解決に大きく貢献していることを示しています。
子どもたちの未来を守るために、ぜひ導入をご検討ください。
気づいたときには、
もう手遅れかもしれません
ある日、あなたの学校で突然、重大ないじめ事件が発覚しました。
「どうしてこんなことに…?」
教師も、保護者も、誰もが言葉を失います。
あなたは、この問題を未然に防げたはずなのに、と後悔していませんか?
しかし、いじめの兆候はどこにあったのでしょう?
あなたは、クラスの空気が悪いことをなんとなく感じていたかもしれません。
でも、はっきりした証拠もなく、対応するべきなのか迷っていた。
気づかないうちに、不安や孤独を抱える子どもが増えていた。
しかし、誰もその「小さなSOS」に気づくことができなかった。
そして、いよいよ教育委員会から「いじめ対策を強化しろ」と指示が出る。
でも、何をすればいいのか分からない。
従来のアンケートでは、核心に触れられない。
さらに、保護者からは「学校は何もしてくれない」とクレームの嵐。
説明しようにも、何を根拠に話せばいいのか分からない。
ただただ、謝るしかない…。
しかし、本当にそれでいいのでしょうか?
学校の環境が悪化し、不登校が増え、子どもたちの学びの場が失われていく。
何も対策をしなければ、同じような問題がまた起こるかもしれない。
でも、まだ間に合います。
手を打つなら、今しかありません。
子どもたちの未来を守るために、いじめや適応の兆候を正確に把握し、
データに基づいた確実な対策を始めませんか?
今なら、あなたの学校を変えることができます。
子どもたちの未来を救えるのは、あなたしかいないのです。
データで見える学校の課題:
改善の第一歩
教育現場の課題を感覚や経験だけで判断する時代は終わりつつあります。データを活用することで、学校全体の課題を客観的に把握し、具体的な改善策を講じることが可能になります。学校現場では、日々多くの課題が発生しています。不登校、いじめ、学級経営の難しさなど、教師一人の観察や経験だけでは対応しきれないことも増えています。そこで注目されているのが、データを活用した課題の可視化と改善です。
データを活用することで、以下のようなメリットが得られます:
客観性の向上:感覚や経験に頼るのではなく、数値やデータに基づいて課題を把握できます。これにより、問題の本質を見誤るリスクが減少します。
早期発見と対策:例えば、アセスやB-SAFEを活用することで、子どもたちの適応感やいじめリスクを早期に把握し、迅速な対応が可能になります。
チーム学校の強化:データを共有することで、教師間や学校全体で共通認識を持つことができます。これにより、一貫性のある支援や指導が実現します。
改善の具体化:データに基づく分析により、具体的な改善策を立案できます。例えば、「学級内の非侵害的関係が弱い」というデータが出た場合、協力活動や対話の場を増やすなど、具体的なアクションプランを立てることができます。
アセスやB-SAFEは、こうしたデータ活用を可能にするツールとして、多くの学校で導入されています。教育現場の課題をデータで見える化し、より良い学校づくりを実現するために、データ活用の重要性を再認識することが求められています。
アセス・B-SAFEの導入手順:
簡単・スムーズなスタート
アセスとB-SAFEは、教育現場での課題解決を支援するために、簡単に導入できる仕組みを整えています。
以下は、導入の基本的な流れです。
-
資料請求・説明会の参加
まずは、アセスやB-SAFEの詳細を知るために、資料請求やオンライン説明会にご参加ください。ここでは、ツールの特徴や活用事例、費用について詳しくご説明します。説明会にご参加いただくと、アセスWEB版・B-SAFEのデモ版を2週間ご活用いただき、導入検討をすることができます。
-
導入プランの選定
学校単位、自治体単位など、ニーズに合わせた導入プランをお選びいただけます。また、試験的に少人数で実施するトライアルプランもご用意しています。
また、将来的な「自立運用」を目指すために、現場の状況やご要望に合わせて、研修(無料・有料)のご提案もすることができます。 -
実施準備
導入が決定したら、実施に向けた準備を行います。ツールの使用方法やデータの取り扱いについては、専任スタッフが丁寧にサポートします。オンラインでの研修も実施可能です。
-
実施とデータ収集
子どもたちにアセスやB-SAFEを実施し、データを収集します。実施は簡単で、短時間で完了します。オンライン環境が整っていれば、Web上での実施も可能です。
-
結果の分析とフィードバック
収集したデータを分析し、結果をレポートとして提供します。教師や学校全体で結果を共有し、具体的な改善策を検討するための参考資料として活用できます。
-
継続的なフォローアップ
導入後も、専任スタッフが継続的にサポートします。データの活用方法や次回実施のタイミングなど、必要に応じてアドバイスを提供します
アセスとB-SAFEの導入は、子どもたちの未来を守るための第一歩です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
学校適応感が子どもの未来を支える理由
学校適応感とは、子どもたちが「学校で安心して過ごせる」「自分は学校で受け入れられている」と感じる感覚を指します。この感覚は、子どもたちの心身の健康や学習意欲に大きな影響を与えます。
学校適応感が重要である理由は以下の通りです:
心理的安全の確保
学校適応感が高い子どもは、心理的に安定しやすく、不安やストレスを抱えにくい傾向があります。これにより、学校生活を前向きに楽しむことができます。
学習意欲の向上
適応感が高い子どもは、学級や学校に対する信頼感が強く、学習意欲が向上します。一方、適応感が低い場合、学習への集中力が低下しやすくなります。
不登校やいじめの予防
適応感が低い子どもは、不登校やいじめの被害者・加害者になるリスクが高いとされています。適応感を高めることで、こうしたリスクを軽減することができます。
アセスは、子どもたちの学校適応感を6つの側面から測定し、課題を明確にするためのツールです。適応感を高める取り組みを通じて、子どもたちが安心して成長できる環境を作ることができます。
学校適応感を重視することは、子どもたちの未来を支えるために欠かせない視点です。誰もが安心して通える学校を目指して、適応感の向上に取り組みましょう。
アセスが変えた学校現場:
成功事例のご紹介
アセスを活用した学校では、子どもたちの適応感が向上し、不登校やいじめの予防につながった事例が多く報告されています。以下はその一例です。
-
事例1:中学校での活用
ある中学校では、アセスを活用して学級全体の適応感を測定しました。その結果、特定の学級で「仲間とのつながり」のスコアが低いことが判明。教師は協力活動を増やし、学級内のコミュニケーションを促進する取り組みを実施しました。その結果、学級全体の雰囲気が改善し、不登校だった生徒が再登校するきっかけとなりました。
-
事例2:小学校での活用
小学校では、アセスの結果から「先生との信頼関係」のスコアが低い子どもが複数いることが分かりました。教師は個別面談を実施し、子どもたちの声に耳を傾ける時間を増やしました。その結果、子どもたちの適応感が向上し、授業中の発言や積極性が増えました。
アセスは、学校現場における課題を可視化し、具体的な改善策を導き出すためのツールです。
これらの成功事例は、アセスが教育現場に与える大きな可能性を示しています。
ぜひ、アセスを活用して、より良い学校づくりを目指してください。

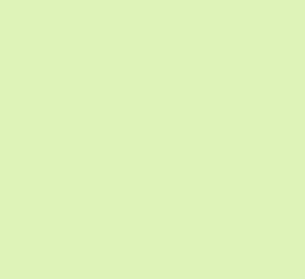
アセスとB-SAFEが描く未来:
子どもたちが安心して学べる社会へ

アセスとB-SAFEが目指すのは、子どもたちが安心して通える学校、そして誰もが自分らしく成長できる社会です。その未来を共に実現しましょう。
アセスとB-SAFEは、教育現場の課題を解決するために生まれたツールです。しかし、その目的は単なる問題解決にとどまりません。私たちが目指しているのは、子どもたちが安心して学校に通い、自分らしく成長できる未来です。
現代の子どもたちは、いじめや不登校、家庭環境の変化など、さまざまな課題に直面しています。その中で、学校は子どもたちにとって「安心できる居場所」であるべきです。アセスとB-SAFEは、子どもたちの声を可視化し、早期に支援を届けることで、学校をより安全で温かい場所に変えることを目指しています。
また、これらのツールは、教師や学校だけでなく、保護者や地域社会とも連携し、子どもたちを支える「チーム」としての役割を強化します。データに基づく共通認識を持つことで、より効果的な支援が可能になります。
「毎日学校に行きたくなる場所を日本中に作りたい。」この願いを胸に、アセスとB-SAFEは、教育現場の新しいスタンダードとして、子どもたちの未来を支え続けます。私たちと共に、より良い未来を築いていきましょう。
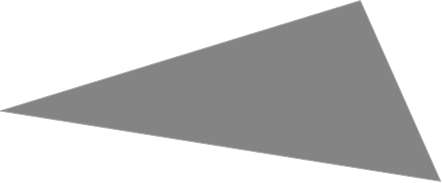
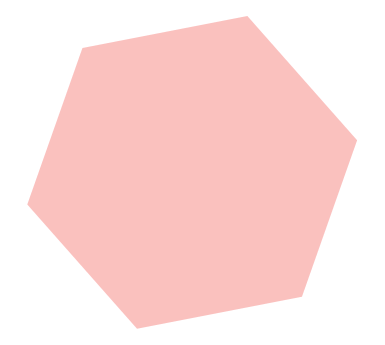
Q&A
1学期にアセスを実施する理由は大きく2つあります。1つは年度当初の適応状態を把握するためです。
もう一つはその結果に基づいて学期後半の支援を再検討し、すべての子どもたちが良い適応状態で学期末を迎えるためです。それには理由があります。
不登校が1番増えるのが9月当初ですが、そうした子供は、夏休みを不適応な状態のままで迎えていることが多いことがわかっています。学級に対して否定的で1学期が「やっと終わった」と思っている子どもは2学期が近づくにつれて憂鬱な気持ちになるでしょう。それが不登校につながります。
こう考えると、実施するのは学級がある程度落ち着いた5月中旬以降ということになります。また、不適応傾向のある子どもへの支援期間も少なくとも一ヶ月はみる必要がありますから、6月上旬には終わっている必要があります。以上を考えると5月の連休明けから6月上旬の一ヶ月が妥当と思われます。ただ、ゴールデンウィーク明けも同じ理由で不登校が急増する時期です。そのことを考えると、気になる子どもがいる場合には、少し早いですが、ゴールデンウィークに入るちょっと前に実施して、早急に手を打つと言うことも考えられます。このあたりは学級の実態を観ながら実施時期を考えて下さい。
3回ぐらいが妥当でしょう。基本パターンは各学期の真ん中当たり、具体的には5月末、11月上旬~中旬、2月中旬です。その理由は、端的に言えば不適応感を抱いたままで長期休みを迎えさせないためです。 学級に対して否定的な感情をもち「やっと終わった」と思って長期休業を迎えた子どもは、新学期が近づくにつれて学校回避感情が高まり、不登校になる可能性が高くなります。そのためには各学期の中盤で不適応傾向の子どもを把握し、適応感を改善する手立てを取る必要があります。
昨年度、学級崩壊でグチャグチャになったクラスを引き継ぎ、1学期間、ともかく子どもたちとの信頼関係を作るために頑張ってきました。学級も何とか落ち着きを取り戻したので、1学期末にアセスを実施したところ、教師サポート得点平均が47で全国平均以下でした。分布は、青が40%、緑が50%、オレンジが10%、赤0%でした。結構ショックで、「これまでの取り組みでは教師としてのサポートは足りなかったのか」と落ち込みました。これはどう解釈したらいいのでしょうか。
学級崩壊をしたクラスでは、教師と子どもの信頼関係が壊れていることが多いです。一度壊れた信頼関係は簡単には回復しませんので、1学期末に教師サポート得点には、前年度の教師不信感が強く影響していると考えられます。
仮に昨年度末にアセスを取っていたとすれば、オレンジと赤で40%前後はあったのではないかと想像されます。それが現状の先生の学級は、オレンジ10%ですし、赤もいません。
赤とオレンジの合算は全国平均で17%程度ですから、前年度の学級崩壊を勘案すると、1学期間で子供たちとの関係は相当に良くなっていると考えられます。
つまり50%を占める緑の子供たちは、「徐々に教師不信から回復してきている子供たち」であると思われます。子供たちの様子を丁寧に観察しながら、今の方向で取り組みを進めていけば良いのではないかと思います。
学校全体でアセスを使用して構わないでしょうか?別途、複数購入したり、申請したりする必要はあるでしょうか?
1冊の『アセスの使い方・活かし方』で使用できるのは原則1クラスですが、購入者が同学年の他のクラスの分を実施することが可能です。なお、アセスの適正な活用のためにも、1冊のアセスで学年を超えての利用は避けてください。
次年度以降に引き続きご使用いただく場合は、新たにご購入する必要はありません。
研修をすることです。
アセスでは、個々の子どもや学級全体の学校適応感の状態について、結果をプリントアウトできます。ただ、①その結果をどう解釈するか、②解釈を生かしてどう支援するか、については詳細には述べていません。
①については、日頃の観察や直接のやりとりの結果とアセスの結果を照らし合わせて判断してください。開発のプロセスでは、教師の観察では「問題なし」とされていた子どもでも、アセスでは「適応上の課題あり」となる子どもも3~4割いました。
これは6~7割程度は教師の観察で子どもの状態は把握できるけれども、教師が見逃しているかもしれない子どもをアセスは拾い上げている可能性があることを示しています。アセスの結果と日頃の観察とのズレを検討することで、より深い子ども理解が可能になると考えられます。
②についてですが、たとえば「非侵害的関係」得点が低い子どもは何らかの原因で”侵害”を感じて苦しんでいることを示します。
それは教師が気がつかなくても、隠れたところで侵害的行為を受けていることを反映しているのかもしれません。だとすれば早急な支援が必要です。また、時には過去の経験から被害妄想的になり、”友だちから無視されることがある”気がするようになっているのかもしれません。
その場合は実際には侵害的行為を受けてはいないことになりますが、苦しんでいるという点では同じです。30点未満の子どもに対しては早急な支援を、40点未満の子どもに対しても、意図的で集中的な支援が必要です。
なお、研修のやり方については、「アセスの使い方・活かし方」(ほんの森出版)の中にも書かれていますし、eラーニングサイトでも研修講座が公開されていますので、そちらをご覧になっていただいてもいいでしょう。
なお、会員になられた方は、AISESの資料であることを明示していただければ、パワーポイントのデータをプリントアウトして校内研修等で使用していただいてかまいません。
「してはいけない」ということではありませんが、「結果は正確ではない」「数値を低く考える必要がある」ことなどを十二分に理解して使用することが重要です。
アセスの開発の際には、小1、小2を対象にデータを取っていますが、最終的には、「小1、小2の回答は信頼性や妥当性の部分で疑問が残る」ので「CD-ROMには入れない」ということにしました。ただ、「小1、小2にも実施したい」という声は多く聞いています。そこで、少し長くなりますが、「では、実施するとすれば、どうすればいいのか」ということについて説明します。
まず第一に、文章の理解力が十分でなかったり、逆転項目(・・・ではない)への回答の仕方が分からないということが考えられます。その場合、「回答が正確でない」可能性が高まります。そこで「簡単に解説をする」「平易な言葉に置き換える」「回答の仕方を説明する」といった配慮が必要になります。
第二に、34項目の質問に対して集中力を維持することが困難になるかもしれません。この場合も「回答が正確でない」可能性が高まります。そこで「2回に分けて実施する」「落ち着いている時間帯を使って実施する」「先生が読み上げながら実施する」といった配慮が必要になります。
第三に、そもそも小1、小2のデータベースがないという問題があります。そうすると、取ったデータを小3のデータベースに当てはめて分析をすることになりますが、一般的に適応感の素点は小3より、小1、小2の方が高いと言う傾向があります。つまり、小3で素点18点の子どもがちょうど真ん中だとしても、小1の場合は素点20点の子どもが真ん中かもしれないということです。ということは、本当は素点20点の小1の子どもを小3と見なして分析すると、本当は偏差値得点は50なのに、53とか、そういう数値になる可能性があるということです。そこで「出てきた数値は低めに解釈する」ということが必要になります。ただ、同じ尺度で測定しているわけですから、「A君とB君ではA君の方が高い」「おおむね良好(あるいはその逆)」といったことは判断は可能でしょう。
第四に、アセスはそもそも学校適応感を6つの側面から測定しています。それは子どもたちが、少なくとも6つの側面を分けて考えていることが前提となります。ところが小1、小2はどうやら6つに分けて考えられないのかもしれないのです。わかりにくいですが、アセスは開発の最初の段階で大学生を対象にデータを取りました。たとえば大学生は、「学校は・・・」「担任の先生は・・・」「学校の先生は・・・」という3つの質問文を分けて考えることができます。
しかし小1、小2の子どもにとっては「学校」も「学校の先生」も「担任の先生」もほとんど同じで、当然区別しないで回答する傾向があるということです。となると、そもそも「6つの側面から学校適応をみる」という前提が崩れてしまいます。これが小1、小2用のアセスを開発できなかった最大の理由です。
たとえば、「仲間に入れてもらえないことがある」と言う質問は非侵害的因子ですが、こういう問題を抱えている子どもは、友人サポート因子の「友だちは、わたしのことをわかってくれる」という質問にNoと回答するかもしれません。非侵害的因子と友人サポートは本来別のものなので、「侵害されていても友人サポートはある」となっていいのですが、それが分かってくるのは小3以降ぐらいで、小1、小2では、「仲間に入れてもらえないことがある」=「友だちは、わたしのことをわかってくれない」となってしまう傾向が強い、ということです。
ということは「回答の一つ一つの質問文を大切に回答を読む」「何かの因子が低い場合は、ひょっとしたらそれ以外のところにも原因があるかもしれないと思いながら解釈する」といったことが必要になります。いずれにしても、「結果を鵜呑みにせず、日頃の観察を大切にしながらデータを解釈する」ことが高学年以上に求められることになります。
以上、長くなりましたが、実施時には「簡単に解説をする」「平易な言葉に置き換える」「回答の仕方を説明する」「2回に分けて実施する」「落ち着いている時間帯を使って実施する」「先生が読み上げながら実施する」と言った配慮を必要に応じて行うこと、また結果が出た後には、「出てきた数値は低めに解釈する」「回答の一つ一つの質問文を大切に回答を読む」「何かの因子が低い場合は、ひょっとしたらそれ以外のところにも原因があるかもしれないと思いながら解釈する」「結果を鵜呑みにせず、日頃の観察を大切にしながらデータを解釈する」といったことを意識することが重要です。
本市は、小学校も中学校も、学校統廃合による学校再編をひかえています。統合前と統合後にアセスを実施した場合、個人特性票を比較検討することで、「統合」が影響した変化を読み取ることができますか?
できます。
人間は、人を含めた環境の中で生活しています。アセスは、それを実施した時点で、子どもが、自分を取り巻く環境をどのようにとらえているかを測定しています。
統合によって「友人との新たな関係」「先生との新たな関係」「学習との新たな関係」が生まれます。それは当然、「統合後のアセス」に反映します。
これと「統合前のアセス」を比較すれば、統合が、その児童生徒にどのような影響を与えているかを推察することができます。
また、個人特性票だけではなく、学級内分布票をみることで、学級全体の状態がわかります・統合後の学級経営が全体としてうまく機能しているのかどうかをみるためには、平均得点だけではなく、学級内分布票の右側の棒グラフを丁寧に検討することが有益だと思われます。赤やオレンジの領域にいる子どもには、特に注意を払いたいものです。
自分の学校の児童生徒のことはわかりますが、別の学校の児童生徒の支援方法が考えられるのでしょうか。
もちろん、可能です。
アセスのデータは、子どもの心理的な適応状態を示しています。いいかえれば、現実の環境に対する子どもの反応ということになります。ですので、アセスのデータが悪いということは、実際に何かうまくいかないことがあると考えればいいということになります。
教員に求められることは、アセスのデータから現実に何が起こっているのかを推察し、仮説を立て、支援策を検討することです。そしてその仮説に沿って子どもを観察し子ども理解を深めていくことになります。
AISESでは、当該の子どもや学級に関わる先生方が集まって、みんなで仮説と支援策を作成することを推奨しています。そうすることで、子供理解と支援方針を共有できるからです。
いくつかの学校の先生方が集まって協議をすることがあるかもしれません。その場合もプロセスは同じです。ただ、子供の実際の状態を見ていないわけですから、プロフィール等を用意した上でディスカッションをすると良いでしょう。同一校内で行う研修会に比べれば、子どもを見ていない分仮説を作るのは難しくなりますが、逆に言えばアセスメント能力が高まると言えるでしょう。支援策については自分の学校の子どもではありませんので、すぐに使えるわけではありませんが、そうした協議をすることで支援の引き出しは増えていきます。また、当該の子どもがいる学校の先生にとっては、他校の先生方の客観的な意見を聞くことができるので、実際、大いに参考になるでしょう。
私の実感としては、アセスは子ども理解の方向転換を図る上で非常に有効だと感じています。
どういうことかと言いますと、多くの場合、教師からすれば「課題のある子ども」は困った子どもであり、指導の対象と思っています。それがアセスを行った後は、「困った子ども」ではなく、問題行動は何らかの困り感の反映であることが理解できるようになります。
つまり、「困った子ども」は、「困っている子ども」「支援が必要な子ども」という見方に変わるということです。ですので、学年団等で結果を共有する時間を設けると、子ども理解を共有することができ、指導の迷いが消え、教員団の指導の一貫性が生まれることが多いです。
表裏印刷を想定しているので、2枚ではなく1枚です。
確かに、印刷に手間がかかるという言い方はできるかもしれません。厳密に言えば、同じ状況での実施を想定しているので、「よいか」と聞かれると「表裏印刷をして、表をみてやり方を統一した上で、裏面に取りかからせてください」ということになります。ただ、口頭での説明を加えると言うことであれば、実質的には大きな問題はないと考えます。
わかりやすい文言を加えると言うこと自体は問題ありません。
その際、「学校生活をもっと気持ちよく過ごせるようにするための」をどう言い換えるかですが、「つまり、勉強の環境をよくするための」だけですと、回答する際にバイアスがかかることを危惧します。本来は学習環境と対人関係の両方なので、「つまり、勉強の環境をよくしたり、人間関係をよくしたりするための」という言い方であれば全く問題はないと思われます。
まず、アセスは直接のフィードバックを想定していません。
なので、そのままは返さない方がいいでしょう。実際に想定しているのは、この結果を生かして子ども理解を深め、より適切な関わりをするようになることです。
たとえば非侵害得点が低い子どもがいた場合、やりっ放しにせず、言い方は考えるとしても、子どもに対して「非侵害得点が低いんだけれども、何か、学校で嫌なことがあるのかな」と問いかけたり、保護者面接の中で「生活満足感というのは、全体的に今楽しく学校や家庭で過ごせているかと言うことを反映しているのですが、この数値が低いんですね。最近表情もぱっとしないし、声をかけたり、様子を観察したりしていますが、ご家庭でも何か気になるようなことはありますか?」といった形で活用することが求められます。逆に数値が低いのに、「返却した」ということを口実に「手を打たない」ことの危険性を危惧します。
保護者は、学習成績への関心は当然高いわけですが、その一方で、「学校での人間関係・いじめ」についても非常に高い関心を持っています。
成績をつける際に、「なぜテストをするのか。私の子どもの能力を勝手に測定するな」と問われたら、「観察だけで成績をつけることの方がむしろ不公平であり適切ではない」と説明するでしょう。テストを実施することが学校にとっては説明責任を果たすことになります。学級経営も全く同じです。学級の状態を多面的に把握して適切な指導をするのは、むしろ学校の説明責任と考えます。このことを教師がしっかりと納得しておけば大きな問題はないでしょう。
また、アセスは個人の能力を測定するような尺度ではなく、対人関係と勉強をうまくやれているかという状態を見る尺度です。ですので、「アセスは、子どもが今の学校で、教師や級友と良好な人間関係を保ちながら、学習に意欲的に向かえているかどうかを確認するためのもので、その結果を生かしながら、学級経営や授業の改善をするために用いるために実施します。」ということで、十分に説明責任は果たせるのではないかと考えます。
まずは解釈の基本を押さえるために、アセスの本を丁寧に読まれることをお勧めします。その上での話ですが「実践をしながらモニタリングを続けて、解釈をより妥当なものに修正していく」と考えて下さい。「正解などない」と思った方がいいかも知れません。また、解釈事例を知りたい場合は、こちらをご覧ください。たくさんの解釈事例が出ています。
「そうは言っても自分の解釈が妥当かどうかを知りたい」という方は、アセスに精通したAISESのスタッフに相談することができます。有償になりますが承りますので、お問い合わせください。
個人が環境に適応する場合、検討しなくてはいけない要素は、大きく言えば個人要因と環境要因ということになります。ただ、この二つの要因は、一人一人全く違うわけですから、支援の手立ては100%オーダーメイド、ということになります。ですので、自分たちで検討していただければと思います。こう書くと若干無責任な感じがするかもしれませんが、具体策を自分たちで協議することこそが重要だと思います。なぜならば、それこそが、支援の方策を生み出す力を高めることだからです。以下に、その一般的な原則をお示しします。これらのことを念頭に、学年会や学校全体で協議して下さい。
- 子どもや親を変化させることはできない。「指導するより、理解し、親や子どもが変わるのを支援する」というスタンスをとること。これがグランドセオリー。
- 本人や親の隠された願いを十二分に聞き取り、理解し、意識すること。それに沿わない支援は空振りに終わる。
- ソーシャルサポートを本人が自覚していない限りなかなか動き出せないのが現実だということを考えて、支援すること。
- こちらが良いと思うこと以上に、本人がやりたい、ありがたいと思う支援でなければ役に立たないことが多いことを意識すること。できれば「こういう関わり方は君にとってプラスか」と本人に聞くと良い。
- 可能な限りスモールステップにすること。 支援が必要な領域は苦手であることが多いし、特に発達障害が背景にある場合は、こちらから見て簡単に思えることでも、本人にとっては困難なことであることが多い。
- 自由な発想で多角的に支援策を考えること。直接的に効果はなくても、状況の改善につながることはいくらでもあることを意識すること。
- 支援の実行は常にチームで。担任任せにして担任を孤立させない。一定期間後に(学年会等で)評価を行うこと。その評価に従って新たな支援策を考えること。
導入プラン
学校単位での導入だけでなく、自治体単位での一括導入も可能です。また、オンライン説明会に参加すると、体験デモ版を2週間無料で利用できる特典もあります。
費用対効果
アセスとB-SAFEは、リーズナブルな価格ながら、子どもたちの適応感やいじめリスクを可視化し、早期支援につなげることができます。これにより、不登校やいじめの予防、学級経営の改善など、教育現場全体の質を向上させることが可能です。
アセスとB-SAFEは、費用対効果の高いツールとして、多くの学校や自治体から支持されています。子どもたちの未来を守るために、ぜひ導入をご検討ください。

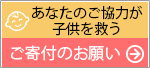




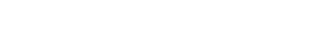

 LINEに追加する
LINEに追加する